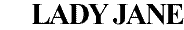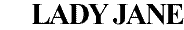|
一九二〇年代のニューヨークは、「朝日のあたる家」という娼家の廃止で、演奏場所を失った地方の多くの黒人ジャズメンと、海外からの異民族が流れ込み、人種のメルティング・ポットだった。時は禁酒法下で、暗黒街は栄え、ハーレムの「コットン・クラブ」では、デューク・エリントンが毎夜、ジャングル・ジャズで客を挑発していた。
奇しくも二八年には、クルト・ヴァイルが「三文オペラ」を。ラヴェルは「ボレロ」を、ジョージ・ガーシュインは「パリのアメリカ人」を作って、時代を象徴づけているが、クラッシック音楽と区別なく、早くからジャズに魅かれ、多数の名曲を残したガーシュインは、エリントンと共に、“アメリカの音楽はジャズだ”という認識を植えつけた張本人だと僕は思っている。第一、ガーシュイン曲を一曲も演奏しないジャズメンはいないはずだ。
で、ガーシュイン生誕百年に当たる今年、歌手の前田祐希が、その名もズバリ「ジャズ・エイジ」というガーシュイン・ソング・ブックを、六月十日、EWEレコードから出した。続けて八月に二枚目をリリースする。十二人のピアニストを選び、一枚のCDに一曲ずつ吹き込んでいるから、二枚で二十四曲の情景が個々の自由発想で描かれ、まるでおもちゃ箱をひっくりかえしたようだ。
前田祐希と初めて会ったのは、八七年八月十五日の「ロマーニッシェス・カフェ」に出演した際だった。ピアノの志津と組んだライブ「デボラ」は、初メジャーCD「ルナ・パーク」と題した、やはりガーシュイン曲集のマスタリングを徹夜明けで終えた、その夜だった。その大人の遊園地的な演奏は、店内の雰囲気にも合い、僕にも新鮮に映ったが、ファルセットを多用したオペラ唱法だったし、気負いもあって、今後の活用範囲に多少の不安は残した。
その後、怖いもの知らずの彼女は、ジャズ現場に割り込んでいくのだが、歌唱法がそのままなので、「その唱法では、ジャズ歌手でも、クラシック歌手でもないよ」と山下洋輔に釘を刺されても、めげずだった。だが、意思とは関係なく、経験と年齢は唱法を変化させ、歌の領域を広げた。で、いままた、ジャズでもクラシックでもないガーシュインによって、彼女はいかされているのである。
九月二十六日のガーシュイン生誕百年に向かって、「スワニー」河に航海に出た前田祐希号を、どんな岸辺が待っているのだろう。
「アサヒグラフ」1998年6月26日号掲載
|