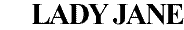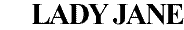|
時代の牽引者として、振り返ることなく一九五〇年代、六〇年代を駆け抜けてきたマイルス・デイビスの変革は、六九年の「イン・ア・サイレント・ウェイ」で新たな転換を迎えた。エレクトロニクスを駆使したファンク・ビートの導入だ。
そして、七〇年代の夜明けを告げる、驚愕の「ビッチェス・ブリュー」の出現。時間感覚を麻痺させる執拗な繰り返しと、アフリカン・ポリリズムに突如、刀のように切り裂くワウワウ・ペダル・トランペットは衝撃だった。でもなぜか、僕が一番好きなのは、七〇年代に出した映画のサウンドトラック「ジャック・ジョンソン」だ。
このアルバムが出たころ、僕はテント演劇の公園で本土復帰直前の沖縄に行き、帰りは船で鹿児島に出て、疲れきった体を慰めに、ジャズ界では知られた「パノニカ」という店で中山信一郎さん宅にお邪魔した。食事をご馳走になり、たばこを一服したとき、目に留まったのが黄色いロールスロイスに数人の白人女性を脇にした、黒人で最初のヘビー級チャンピオンになった「ジャック・ジョンソン」のジャケット写真だった。
アルバムを初めて手にした僕は、マイケル・ヘンダーソンの重低音ベースと、ジョン・マクラフリンのやたらサイケデリックなギター、射るような乗りのいいマイルスの幻覚的サウンドで、翌日から始まるテント演劇のために、エネルギーを充填した。
「イン・サイレント・ウェイ」で、ちょっとマイルスと離れた守旧派ジャズ評論家は、たて乗り8ビート、ほとんどロックのこのアルバムで、完全にしっぽを巻き、ジャズ・ミュージシャンの多くもマイルス離れを始めた。僕の学校と自称していた新宿ゴールデン街でも、マイルス評価を巡ってよく喧嘩をしたが、「中山さんのような開けた評論家もいるんだ」と、うれしくなった。
また、写真家として「初めてバイブレーションを感じた」という吉田ルイ子は、数あるアルバムの中から、「ジャック・ジョンソン」を選んでいるし、マイルスの残したネタは「タダで使わせてもらうが、二十一世紀シーンにお返ししたい」という近藤等則も、同じ気持ちに違いないと確信する。ロック・ファンが殺到し、ジャズ・ファンが背を向けたこのアルバムは、どちらからもまま子扱いのようだ。
マイルスは平然と言った。「俺のことをジャズマンと呼ぶな」と。
「アサヒグラフ」1998年2月27日号掲載
|