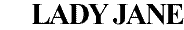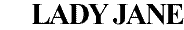|
昨年(1997)、僕のとくに愛着のある一軒の店がなくなった。映画や芝居や音楽を観たり聴いたりした後、よく通った。
中野の新井薬師近くにあった「広重」というその料理屋は、引き戸を開けると、すぐ土間に三、四人掛けの長椅子があり、奥のあがり框(かまち)に四畳半が控えるといった、二組で満席の極めてつましい造り方だった。そこで供される江戸立場料理という立場とは、昔、街道で人夫が駕篭などを止めて休息する立場茶屋の意からきているのだが、江戸っ子気質の粋なおかみさんの仕切りもあって、常に凛とした空気に包まれていた。
もちろん、ちゃんちきおけさはご法度だ。緩やかな緊張状態の五感に、その日、見聞きしたステージの音や映像や台詞が、夾雑物なくかぶさってきて、余韻にひたれるのだった。
二十世紀が生んだ偉大な異端の音楽家、アストル・ピアソラの高揚と安穏のバンドネオンにすがるように、ジャンニ・ベルサーチのサテンの薄物一枚を身にまとった裸足のミルバが、苦痛と陶酔を歌い踊るのを観ての帰り。「あの二人、絶対デキてるよな」と、僕はいって酒盃を口にする。「そう思うと」と、連れはこたえて箸を手にした。まるで、イサドラ・ダンカンが復活したかのようなミルバの激情の振り子は、ピアソラが創る振幅にピタリと呼応していた。一体化し溶け合った二人の魂は、僕らを取り込み、いま「広重」までついてくる。ピアソラと、「広重」というミスマッチは、逆に心地よい刺激を生む。
また「テアトロ・ド・コンプリシテ」というイギリスの劇団の「ルーシー・キャブロルの三つの人生」の技術的に上がりつめた身体表現や、グループ「オフィチウム」のグレゴリオ聖歌の音楽表現が、悲しいまでに天空に吸収されていく生の喜びを感知したとき、「広重」の膳は、癒しの膳になるのだった。
閉店の三月三一日、僕は最後の客だった。「形見分けですから、何でも好きなものを」と、おかみにいわれるまま、江戸提灯やら皿を持ちかえったのだが・・・・・・。
初めてこの店を訪ねたのは、映画「それから」の完成試写を見終わった八五年のある日、同映画の主演俳優・松田優作とともに、脚本の筒井ともみに連れてこられたときだった。それゆえに、以後、梅林茂作曲の「それから」のテーマは、ずっと鳴り続けることになるわけだが、ステージの余韻を疎外することはなかった。
「アサヒグラフ」1998年2月6日号掲載
|